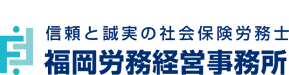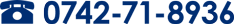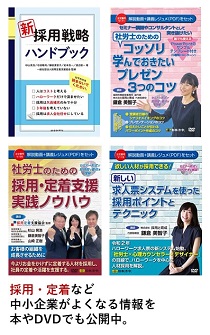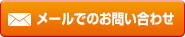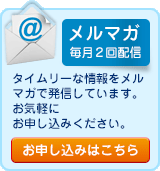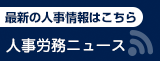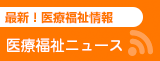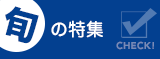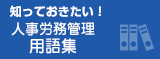�����p��̘J���o�c�R����
�����J���o�c�������@�����p�ꂪ���X�̏��𒆐S�ɋL�ڂ��Ă䂫�܂��B2025�N8���P�P���i���j
�ږ�_��̒��Ŗڎw������
�����J������グ�̂V�O���͌ږ�_��̂��q�l���炢�����������̌ږ◿�ƂȂ��Ă��܂��B
���̑��͏A�ƋK���̍쐬�E�������A���������p�ɂ����̂������ł��B
�J���g���u���͖��R�h�~�ɗ͂����Ă���A�ږ��ł͂܂��J���g���u���͏��Ȃ��A
�J���g���u���̌��O�̂�����̂͑����i�K�ʼn����ɓ�����܂��B
����E���C�����˗�������Ύ��{���Ă���܂��B
�ږ�_����������i�K�ł́A���̊�Ƃ̘J��������������q�A�����O�����܂��B
���̒��ŁA�ۑ�ƂȂ���̂������Ă��āA�ꏏ�ɂȂ��ĉ����̂��߂̃V�i���I�����܂��B
�������x�͂��̂悤�Ȏd�g�݂ɂȂ��Ă��邩�H
�ΑӊǗ��͂ǂ�����Ă��邩�H
�K���ɊǗ�����Ă��邩�H
�������c�Ƃ͔������Ă��Ȃ����H
�J���ی���Љ�ی��̉����͓K���H
�ܗ^�́H�ސE���́H
�������̒��ߓ��́H�x�����́H
�J�����S�q���̖��
�n���X�����g��A
�����̋K��
���d�v�ł��B
���̂悤�Ɍ���͂��Ă䂭�Ɖۑ肪���炩�ɂȂ�A
�A�ƋK���̍쐬�E����
�������x�̌������A�Ɏ��邱�Ƃ������ł��B
�J�������ʒm�����ٗp�_���������܂��B
���ގЂ̎葱�����d�q���ɂ��v�������m�Ɏ��{���܂��B
���a�蓖���A�J�БΉ��A�玙���t���̑Ή��Ȃǂ��X�s�[�f�B�[�ɑΉ����܂��B
���^�v�Z������ꍇ�������ł��B
���^�S���҂��}�ɑސE���ꂽ�ꍇ�ȂǁA��Ƃ͑Ή��ɋꗶ����܂��B
���̈Ӗ��ŁA�����J���o�c�������͎ЊO�l�����Ƃ��Ă̘g�����ʂ����Ă���ƌ�����ł��傤�B
���X�̋Ɩ��ŐE������̏��悭�c�����Ă���̂ŁA
���������^�C�����[�ɂ���Ă��ł��܂��B
2025�N4��20���i���j�`�S��22���i�j
M&A�ƎЉ�ی��J���m�̖���
M&A�ɍۂ��ẮA��Ƃ��l�i�]�ƈ��j�E���x�i�A�ƋK��������̌n�j�E�����i�E�ꕗ�y�j�̓��������ۂ����E���܂��B
📋 M&A�ɂ�����J���f���[�f���W�F���X �`�F�b�N���X�g
�P�D�J���_��E�ٗp�`�Ԃ̊m�F
-
�ٗp�_���S�Ј��ƒ�������Ă��邩
-
�ٗp�`�ԁi���Ј��A�_��Ј��A�p�[�g�E�A���o�C�g�A�Ɩ��ϑ��Ȃǁj�̕��ނ͖��m��
-
���p���ԁA�X�V�����A�_�����̑Ή��͖@�߂ɏ������Ă��邩
-
�O���l�J���҂̍ݗ����i�ƘJ���������K�@��
�Q�D�A�ƋK���E�J�g����̐���
-
�ŐV�̏A�ƋK�����J��ɓ͏o�ς݂�
-
����J�����ԁE�x���E�x�ɐ��x�̖��m�ȋL�ڂ����邩
-
36����i���ԊO�E�x���J���Ɋւ��鋦�菑�j�������E�͏o����Ă��邩
-
�J�g����i�ό`�J�����Ԑ��A�ٗʘJ�����Ȃǁj�̓��e�Ɖ^�p����v���Ă��邩
�R�D�������x�E�x���̊m�F
-
�����K������������Ă��邩�i��{���A�蓖�A�ܗ^�A�ސE���j
-
�Œ�c�Ƒ㐧�x���K�@�ɉ^�p����Ă��邩
-
�����䒠�ƋΑӋL�^�̐����������邩
-
�Œ�����E���������̖@�߈ᔽ���Ȃ���
�S�D�Љ�ی��E�J���ی��̉�����
-
���N�ی��E�����N���ی��A�ٗp�ی��A�J�Еی��ɐ������������Ă��邩
-
�K�Ј��̎Љ�ی��K�p���f���K����
-
�ٗp�ی��E�J�Еی��̔N�x�X�V�A�Љ�ی��̎Z���b�̗͂��s��
�T�D�J�����ԁE�ΑӊǗ��̎���
-
�^�C���J�[�h�E�ΑӃV�X�e���̓�����
-
�c�Ǝ��Ԃ̏���Ǘ��i�ߘJ�����C�����߂��Ȃ����j
-
�L���x�ɂ̊Ǘ��E�擾�i�N5���擾�`���Ȃǁj
-
�J�����Ԃƒ����̕s��v���Ȃ���
�U�D�l���]���E���فE�����̗����Ɛ��x
-
�l���]�����x������A�^�p���K����
-
���������̋L�^������A�A�ƋK���Ɛ������Ă��邩
-
���فE�َ~�߁E�ސE�Ɋւ���g���u����i�ׂ̗L��
�V�D���S�q���E�n���X�����g�Ή�
-
���S�q���Ǘ��̐��i�Y�ƈ�E�q���ψ���E�X�g���X�`�F�b�N�Ȃǁj����������Ă��邩
-
�p���n���E�Z�N�n�����k�����̐ݒu�ƑΉ��}�j���A��
-
�J�Ў��́E�����^���w���X�֘A�̋x�E�E���E�Ή��L�^�̗L��
�W�D�ߋ��̘J���g���u���E�i�ׁE�s���w��
-
�J����ē�����̐��������E�w�����̗L��
-
�Ј��⌳�Ј�����̘J�g�����A�J���R���A�i�ׂȂǂ̗���
-
�ږ�ИJ�m��ٌ�m�̑Ή������̔c��
�Q�O�Q�T�N�S���T���i�y�j
�����J���o�c�������͏������ɋ����Љ�ی��J���m�ł��B
��Ƃ̂��܂��܂Ȏ��g�݂Ɋ��p�ł���u�ԍϕs�v�̏������v�B
�����J���o�c�������ł́A���ۂɎg���鏕�����J�ɂ��ē����A�\������܂ň�уT�|�[�g�������܂��B
✅ ����Ȏ��ɂ͂����k��������
�u����Ȏ��A���������g���邩���H�v�Ƃ�����ʂ͂�������܂��B
���������A�œK�ȏ��������x������Ă��܂��B
-
���グ�����������A���炦�鏕�����͂��邩�H
�@→ ��F�Ɩ����P�������A�L�����A�A�b�v�������i�����K�蓙����R�[�X�j -
�o�Y�E�玙�ɓ���Ј������邪�g���鏕�����͂��邩�H
�@→ ��F�����x�����������i��x�擾���E�E�ꕜ�A���j -
�z��҂��o�Y�\��B�j���Ј����玙�x�Ƃ��擾���邪�A�������͂��邩�H
�@→ ��F�����x�����������i�o���������x���R�[�X�j -
���x�Ƃ��Ƃ肽���E�������邪�g���鏕�����͂��邩�H
�@→ ��F�����x�����������i��엣�E�h�~�x���R�[�X�j
���C�y�ɂ����k���������B
��Ђ̎��g�݂ɍ�����������������Ă������܂��B
�Q�O�Q�T�N�S���S���i���j
�����x�����������@�o���������x���R�[�X�i�q��ăp�p�x���������j�ɂ���
�玙�x�Ƃ��擾���₷���ٗp�������Ȃǂ��s���A
�j���J���҂��玙�x�Ƃ��擾�����ꍇ�Ɏł��鏕�����ł��B
��P��@�j���̈�x����
�@�v���F�ΏۘJ���҂��q�̏o����A�W�T�ȓ��Ɉ�x�J�n
�@�x���z�F�P�l�ځ@�Q�O���~�@�Q�E�R�l�ځ@�P�O���~
��Q��@�j���̈�x�擾���̏㏸��
�@�v���F��x�擾�����R�O���ȏ�UP���T�O���B����
�@�x���z�F�U�O���~
�@
�@����Q��͂P���Ǝ�ɂ��P�����̎x���ł��B
�@����Q��\����̑�P��\������ѓ���N�x���ɑ�P��E��Q�헼���̐\���͂ł��܂���B
�@����P��̑ΏۂƂȂ�������̈玙�x�Ǝ擾�҂̓���̈玙�x�Ǝ擾�҂̓���̈玙�x�Ƃɂ��āA
�@�@�玙�x�Ɠ��x���R�[�X�i��x�擾�����j�Ƃ̕����͂ł��܂���B
�Q�O�Q�T�N�S���R���i�j
���c�Ƒ�͂P���P�ʂ̎���ł��B
�c�Ƒ���P���P�ʂŕ����̂Ƃ����̂͂ǂ����D�ɗ����Ȃ��Ǝv���Ă����B
���Ƃ��A�ߌ�U���I�Ƃ̉�ЂłU���P���Ƃ��U���Q���Ƃ���
�^�C�����R�[�_�[�Ȃ�A���̊Ǘ��V�X�e��������������Ƃ����āA
�Ȃ�������c�Ƒ�Ƃ݂Ȃ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂��H�I
���傤�ǂU���ɉ������Ǝv������A�U���O�ɂ͎d������߂āA
�������������Ă��Ȃ��Ɖ����Ȃ��B
�������A���������Ƀ^�C�����R�[�_�[�Ȃ�A�V�X�e�����u�̂Ƃ���ɐl��������������A
�܂��܂��莞�ɑō�����͍̂���ƂȂ�B
�܂��A�ʂ̌���������A���Ԓ��A���ʂȎ��Ԃ��̎蔲����������
�d���ɖv�����Ă��邩�ƌ�������Ȃ��Ƃ͂Ȃ��낤�B
�ӊO�Ǝ���������̂ł������ł���B
�l�ɂ���Ă͉����������Ă��邱�Ƃ�����B
�܂��A�c�ƃ}���ɂȂ�ƁA�d�������I�Ȃ��Ƃ��̋��E�������܂��ɂȂ�B
�c�Ƃ͎�����m���Ă��炤���Ƃ���Ƃ��������ʂ�����̂ŁA
�S���t�̘b��������A���Ԙb�����邱�Ƃ�����B
����炷�ׂĂ��J�����ԂƖ{���Ɍ�����̂��H
�����������Ƃ������o������A�ʂ����ĘJ�����Ԃ��ĉ��H�Ƃ����^����N���B
�Ƃ��낪�A���̒��͂P���P�ʂ̕����Œ����ɐi��ł���B
���ɃV�X�e�����p���嗬�ɂȂ��Ă���ƁA�P���P�ʂŊ���邱�Ƃ���ԂɂȂ��Ă����B
��ɂU���P���Ƃ��U���Q���̂P����Q�����c�ƂȂ̂��Ƌ^���悵�����A
�����������[�Ȏ��Ԃ͍��v���Ă������������Ƃ͂Ȃ��B
����ł��납�A�Ⴆ�A�R�O���P�ʂƂ��Ă����ЂŁA
�Q�O�����炢�ŏI����̂ɁA
�R�O���ɂȂ�܂Ŏ��Ԃ��Ԃ������Ƃ������S���������Ƃ���A
�t���ʂł���B
����₱���l���āA�P���P�ʂŊ�����Ă��܂��A
���̊Ԃɂ���������ɂȂ��Ă��܂��B
�������c�Ƒ�ői������S�z���Ȃ��Ȃ�B
�����Ƃ��A�X���n�Ƃ̉�ЂŁA
�X���O�ɓ������瑁���c�ƂƂ����l�������邪�A
����͎��͍̗p���Ȃ��B
�d�Ԃ�o�X�̓������Ԃ�Ԓʋ̏ꍇ�̍���ȂǁA
���ɂ���Č덷���o�悤�Ƃ������́B
�������߂ɗ���͓̂�����O�ŁA������Ƃ����đ����c�ƂƂ����͓̂�����Ȃ��B
�Q�O�Q�T�N�S���Q���i���j
���̌Œ�c�Ƒ�蓖�͖����ł��B
�y�����z
��{���R�O���~�i�������A�Œ�c�Ƒ�蓖�S�T���ԕ����܂ށj
��{���R�O���~�ɑ��A�c�Ƒ�𐿋������\��������܂��B
�y�L���z�@
��{���Q�R���~�@�Œ�c�Ƒ�蓖�@�V�S�C�S�S�O�~�i�S�T���ԕ��j
�v�Z���@�Q�R���~÷�P�V�R�D�W���ԁi�����Ϗ���J�����ԁj×�P�D�Q�T×�S�T����
���V�S�C�S�S�O�~
�����}�K�Q�O�Q�T�N�S���P����
4���̂��d���J�����_�[�����J���܂����B�����͐V���Ј������Ђ��A����
�S���҂ɂƂ��Ă͓��Ђɔ������ނ��o���Ă��炤�ȂǑ����̋Ɩ����d�Ȃ�
�����ɂȂ�܂��B�Г��ŃR�~���j�P�[�V�������Ƃ�Ɩ��̒��������Ȃ���i
�߂Ă����܂��傤�B
↓3��25�����J�̂��d���J�����_�[�͂����炩��I
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/i3ouah63ozr5
������
��2.����2025�N�x�̌ٗp�ی������ƒ����̍l����
��������������������������������������������������������������…�d�E
�@�ٗp�ی������͍����ɉ����Ė��N�x�A���������s���Ă��܂��B�ȉ�
�ł́A���肵��2025�N�x�̌ٗp�ی������ƁA�ٗp�ی����̑ΏۂƂȂ������
�ɂ��Ċm�F���܂��B
↓4��1�����J�̃j���[�X�̑����͂����炩��I
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/fvb9b063ozr5
������
��3.����4���ɑn�݂����玙���Z�A�Ƌ��t��
��������������������������������������������������������������…�d�E
�@���悢��2025�N4��1�����V���Ȍٗp�ی��̋��t���ł���u�玙���Z�A��
���t���v���n�݂���܂��B���̋��t���́A2�Ζ����̎q�ǂ���{�炷�邽��
�ɏ���J�����Ԃ�Z�k���āE�E�E
↓3��25�����J�̃j���[�X�̑����͂����炩��I
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/n1c8i163ozr5
������
��4.����3�����ȍ~�̋����ۂ̌��N�ی������E���ی�����
��������������������������������������������������������������…�d�E
�@�S�����N�ی�����̌��N�ی���������щ��ی������́A��N3��������
���������s���Ă��܂��B�ȉ��ł́A2025�N3��������ύX�����s���{��
�x�����̕ی����������`�����܂��B
↓3��18�����J�̃j���[�X�̑����͂����炩��I
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/b37hzj63ozr5
������
��5.�����]�ƈ������Ђ���ۂɍs���ׂ��@�I�葱���Ƃ��̗��ӓ_
��������������������������������������������������������������…�d�E
�@2������1��X�V���Ă���u�{�̓��W�v���X�V���܂����B����́A�u�]��
�������Ђ���ۂɍs���ׂ��@�I�葱���Ƃ��̗��ӓ_�v���Ƃ�グ�܂����B
���e���m�F���Ă����܂��傤�B
↓3��27�����J�̏{�̓��W�͂����炩��I
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/0ge7v063ozr5
������
��6.�����������߃��[�t�F�ߘa7�N4���ȍ~�ɋ���P��������ꍇ�A
���@�@�������t��������������A��{�蓖���ł��܂�
��������������������������������������������������������������…�d�E
�@����̂������߃��[�t���b�g�́u�ߘa7�N4���ȍ~�ɋ���P���������
���A���t��������������A��{�蓖���ł��܂��v�ł��B4�����A�戵
�����ς�邱�Ƃ�����e���m�F���܂��傤�B
↓�u�ߘa7�N4���ȍ~�ɋ���P��������ꍇ�A���t��������������A��{
�@�蓖���ł��܂��v���܂ސl���J���Ǘ����[�t���b�g�W�͂����炩��I
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/vjeh3i63ozr5
��…�d�d…��…�d�d…��…�d�d…��…�d�d…��…�d�d…��…�d�d…��…�d�d
�҄��W���ㄫ�L��
����������������
�@����A�J�����S�q���K������������A��Ƃɑ���M���Ǒ����t��
�ŋ`���t������\��ł��B���N6���Ɏ{�s�����\��ł��邱�Ƃ���A��
�߂ɑ���������܂��傤�B
��������������������������������������������������������������������
�� �s ���F�����J���o�c������
�@�@�@�@�@�@��631-0805�@�ޗnj��ޗǎs�E��4����4-19
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@TEL 0742-71-8936
�� �s �l�F�����p��@info@f-roumu.jp
�z�[���y�[�W �Fhttp://www.fukuoka-roumu.com/
��������������������������������������������������������������������
�����ЁA���ӌ��E�����z��info@f-roumu.jp�܂ł����肭�������B
�������N��́A���ׂē��������̃z�[���y�[�W�ƂȂ��Ă���܂��B
��������������������������������������������������������������������
�Q�O�Q�T�N�S���P���i�j
�@�ٗp�ی������͍����ɉ����Ė��N�x�A���������s���Ă��܂��B
�ȉ��ł́A���肵��2025�N�x�̌ٗp�ی������ƁA�ٗp�ی����̑ΏۂƂȂ�������ɂ��Ċm�F���܂��B
[1]2025�N�x�̌ٗp�ی�����
�@�ٗp�ی������́A�V�^�R���i�E�B���X�����g��̉e���ňꎞ�I�Ȉ���������ꂽ���̂́A�����̉������邱�Ƃ���A2025�N�x�͉��\�̂Ƃ���A�O�N�x����������ƂȂ�܂��B
2025�N�x�̌ٗp�ی�����
| �]�ƈ����S | ��Е��S | ���v | |
| ��ʂ̎��� | 5.5/1,000 | 9/1,000 | 14.5/1,000 |
| �_�ѐ��Y�E�����̎��� | 6.5/1,000 | 10/1,000 | 16.5/1,000 |
| ���݂̎��� | 6.5/1,000 | 11/1,000 | 17.5/1,000 |
[2]�ٗp�ی����̑ΏۂƂȂ����
�@�ٗp�ی����̑ΏۂƂȂ�����Ƃ́A�����A�蓖�A�ܗ^�A���̑����̂��킸�J���̑Ώ��Ƃ��ĉ�Ђ��]�ƈ��ɑ��x�������ׂĂ̂��̂��w���܂��B
�@��{����e��蓖�͂������̂��ƁA��ېłł���ʋΎ蓖���ΏۂƂȂ�܂��B�܂��A���������̎Z���b�ɂ͊܂܂�Ȃ��Z��蓖��Ƒ��蓖���ΏۂƂȂ�܂��B
�@���^��ʉ݂ł͂Ȃ��A�������^�Ƃ��Ďx������Ƃ��ɂ́A�����������̂́A�����Ƃ��Ē����ɊY�����܂���B
�@�������A����������z�����ۂ̔�p��3����1��������Ă���ꍇ�́A���۔�p��3 ����1�ɑ�������z�ƒ���������z�Ƃ̍��z�������A�����Ƃ��Ď戵���܂��B
�@���ۂ̔�p��3����1�������������Ă�����̂͌������^�Ƃ��Ĉ����܂��� �B
[3]���E�[���ɋL�ڂ������
�@�ٗp�ی����̑ΏۂƂȂ�����̂����A�u�Վ��Ɏx����������v�Ɓu3����������Ԃ��ƂɎx����������v�����������̂����E�ؖ����i������u���E�[�v�j���ɋL�ڂ�������ł��B
�@�u�Վ��Ɏx����������v�Ƃ́A�x������邱�Ƃ��܂�ł��邩�A�s�m���ł�����̂������܂��B
�@�܂��A�u3����������Ԃ��ƂɎx����������v�Ƃ́A�����̒�����^�ȊO�̒����̂����A�N�Ԃ�ʂ��Ă̎x����3 ��ȉ��̂��̂ŁA������u�ܗ^�v���w���܂��B
�@���̂��߁A�A�ƋK�����ɂ��N�Ԃ�ʂ���4 ��ȏ�x�������ꍇ�́A3����������Ԃ��ƂɎx����������ɊY�����Ȃ����ƂƂȂ�A���E�[���ɂ����Ắu�����Ɋւ�����L���� �v�Ƃ��ċL�ڂ��K�v�ł��B
�@�ٗp�ی����̑ΏۂƂȂ������A���E�[���ɋL�ڂ�������ɂ��ẮA���i���Ԃ��@����܂�Ȃ����Ǝv���܂��B
�@���̋@��ɓK���ȏ��������Ă��邩���m�F���Ă݂�Ƃ悢�ł��傤�B
2025�N�R���R�P���i���j
�ސE��ƑސE�͂͂ǂ��Ⴄ���H
�ȉ��̂悤�Ɂu�ސE��v�Ɓu�ސE�́v�ɂ͖��m�ȈႢ������܂��B
🔹 �ސE��i�������傭�˂����j
�Ӗ��F
��Ђɑ��āu�ސE�����Ăق����v�����肢���鏑���ł��B
�|�C���g�F
-
��Ђ̏������K�v�i����o���Ă��P�\�j
-
��ɉ~���ސE������~�߂̉\��������ꍇ�Ɏg����
-
�u�܂��m��ł͂Ȃ��i�K�v�ŏo�����Ƃ�����
�ᕶ�F
�u��g��̓s���ɂ��A���������������đސE�����Ă������������A���肢�\���グ�܂��B�v
🔸 �ސE�́i�������傭�Ƃǂ��j
�Ӗ��F
��Ђɑ��āu�ސE���邱�Ƃ�ʒm����v�����ȏ����ł��B
�|�C���g�F
-
��o�������_�������P��ł��Ȃ�
-
��Ђɑ���u�ŏI�ӎv�\���v
-
�@�I�ɂ́A�J���ґ��̈���I�Ȉӎv�\���ł��L��
�ᕶ�F
�u���̂��сA��g��̓s���ɂ��A�ߘa���N���������������đސE�������܂��B�v
2025�N�R���R�O���i���j
�玙���x�ƋK���̉����ɂ���
�ߘa�V�N�S���A�P�O���Ɉ玙���x�Ɩ@�������ɂȂ�܂��B
�M�Ёi�M���Ə��j�ł́A�玙�x�Ɩ@�̉����͂��ςł����H
�����܂��Ȃ�A�����J���o�c�����������J�ɂ��w�����������܂��B
���̋@��ɑ��̏A�ƋK�����������������Ƃ��낪�����ł��B
���̂悤�Ȏ��_���猩�āA�M�Ёi�M���Ə��j�̏A�ƋK���͑��v�ł����H
���A�ƋK�����ȑO������܂܂ōX�V�ł��Ă��Ȃ��Ƃ��������Ƃ͂���܂��H
���c�Ɨ��̓K���Ȍv�Z���ɑΉ����Ă��܂����H
���������x�⎩�Ђ̘J�����f���Ă��܂����H
���玙�E���x�ƋK�����̖@�����ɑΉ����Ă��܂����H
�A�ƋK���͘J���g���u�������Ђ���鏂�ɂȂ�܂��B
�o����x�Ǝx�����t���ɂ���
�ߘa�V�N�S���P������x�����邱�Ƃ��ł���u�o����x�Ǝx�����t���v�ɂ��āA
���[�t���b�g�����\����܂����B
�u�o����x�Ǝx�����t���v�́A�������E����Ă𐄐i���邽�߁A
�q�̏o������̈����ԂɁA���e�Ƃ��� �i�z��҂��A�J���Ă��Ȃ��ꍇ�Ȃǂ͖{�l���j�A
14���ȏ�̈玙�x�Ƃ��擾�����ꍇ�ɁA�o�����玙�x�Ƌ��t���܂��͈玙�x�Ƌ��t���ƕ�����
�u�o����x�Ǝx�����t���v���ő�28���Ԏx���������̂ł��B
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
2025�N3��28���i���j
�ИJ�m�ւ̕s���ɂ���
���̎ИJ�m�ɑ��Ė�������Ă��܂����H
�悭����ȕs�����܂��B
�����k�������Ƃɑ��������Ȃ�
�@���������ɑ��k�����邪�A�����ȉ����Ă���Ȃ��B
�@�܂��A�A�ƋK���ɏ����Ă���Ƃ����������I�m�ȉ������Ȃ��B
�@����������ӂ�ŐM���ł��Ȃ��B
�����^�v�Z�̃~�X�������B
�@���^�v�Z���˗����Ă��邪�~�X�������B
�@���^�v�Z���˗����Ă��ł��Ȃ��ƌ����Ēf����B
���������̊��p�����Ă���Ȃ��B
�@�������̒�Ă��Ȃ��A�L���ȏ��������������Ă��܂����B
���J���N�����������̒��������������̑ԓx������Ȃ��B
�@�J���N�����������̌��������������̑ԓx������Ȃ��B
�@������������܂�M���Ă��Ȃ��悤���B
���J���g���u�����N���������I�m�ɑΉ����Ă���Ȃ������B
�@�J���g���u���ɑ��āA�����Ă�����ɂȂ炸�A�����̎d���������Ă���Ȃ������B
���Ɖ�ɑ��郌�X�|���X���x���B
�@�Ɖ�����Ă����X�|���X���x���A�i�����킩��Ȃ��B
�@���ɂȂ�����������Ă����̂����킩��Ȃ��A�s���ɂȂ�B
�����̂���肪���x�[�X�����S�őΉ����x���B
�@���x�[�X�̎戵�������S�őΉ����x���B
�@IT���A�N���E�h���ɑΉ��ł��Ă��Ȃ��B
���ږ◿�͈��������e���s�\����
�@�ږ◿��������A������̊��҂��邱�Ƃ����Ă��炦�Ȃ��B
���l����@�����̊Ǘ����s���B
�@�l����@����K���ɊǗ�����Ă��邩�ǂ����s�����B
���J���č������Ăق������A�f��ꂽ�B
2025�N3��27���i�j
�A�ƋK���͖��S�ł����H
�@�A�ƋK���͖��S�ł����H
�@�܂��A�@�������ɏ������Đ₦�������������Ă��܂����H
�@�]�ƈ�10�������̉�Ђł͏A�ƋK���̍쐬�y�јJ����ē��ւ̓͂��o�`�����Ȃ��Ƃ���Ă��܂����A
�A�ƋK���̒�߂��Ȃ��悤�ȉ�Ђŏ]�ƈ��͈��S���ē������Ƃ����܂���B
�@�̗p�����܂��䂩���A�Ј��̃��`�x�[�V�������オ�炸�A�ގЎ҂����o���錋�ʂƂ��Ȃ肩�˂܂���B
�@�܂��A�����ɘJ���g���u�������������ɏA�ƋK�����Ȃ��悤�ł́A
���̌��@���Ȃ����傤�Ȃ��̂ŁA������傫�����錋�ʂƂ��Ȃ�܂��B
�@�����A�����J���҂̏����������p���邱�Ƃ������ł����A
����ɂ��A�ƋK���̒�߂��O��ɂȂ�܂��B
�@�A�ƋK�����������A���邢�͖��쐬�̉�Ђɂ����ẮA���̎Љ�ی��J���m�ɂ����k����邱�Ƃ������߂��܂��B
�Q�O�Q�T�N�R���Q�U���i���j
36����̎葱���B�X�V�ɂ���
�@36����́A�T��1�N�Ԃ�L�����ԂƂ��Ă���P�[�X�������̂ŁA
�N�Z���A�L�����Ԃ�K���m�F���A�x�Ȃ��J����ē��ɓ͂��o��悤�ɂ��܂��傤�B
�@�J����@�ł́A�@��J�����Ԃ�1��8���ԁA1�T��40���ԁA�T1���̋x�����߂Ă��܂��B
�@���̎��Ԃ��Ă̘J���́A�J�g�����������A�����J����ē��ɓ͂��o�����邱�Ƃ��K�v�ł��B
�@�܂��A�ʏ�A��45���ԁA�N360���Ԃ��Ďc�Ƃ�����ꍇ�A
��ʂ�36����ȊO�ɓ��ʏ����t��36����̒�o���K�v�ƂȂ�܂��B
�Q�O�Q�T�N�R���Q�T���i�j
�S���͔N�x�n�܂�̉�Ђ������ł��ˁB
�����ŁA�J���Ǘ��𒆐S�ɉ������Ă����������Ƃ����Ă݂܂��傤�B
���V���Ј��̓��Ў葱��
�@�V���Ј��̍��̈�ۂ͋���ł��B
�@�V���Ј����C�����{������Ƃ��������̂ł��B
�@���Ђ������̈�ۂ͈ꐶ�Y��Ȃ����̂ł��B
���J�������ʒm�����ٗp�_�̍쐬
�@�J���_��͌o�c�҂ƘJ���҂Ƃ̂������̌_��s�ׂƂ������܂��B
�@�K�v�ȘJ�������ʒm�����ٗp�_���쐬���ĘJ�g�o����������Ċm�F���Ă����܂��傤�B
�@�l�����ŐV�̂��̂ɂȂ��Ă��邩�ǂ����m�F���Ă����܂��傤�B
���N���L���x�ɂ̕t�^
�@�N���L���x�ɂ͓��Ќ�U�����A���̌�P�N���Ƃɕt�^�������̂ł����A
�N�ɂP��A���邢�͂Q��A����̌��ɍX�V����d�g�݂ɂ��Ă���Ƃ��������܂��B
�@�S���ɍX�V����d�g�݂̂���Ƃ���͍X�V�����Ă����܂��傤�B
��������N�f�f�̎��{
�@������N�f�f�͓��Ў��A�y�єN�P��A����I�Ɏ��{���邱�ƂƂȂ��Ă��܂��B
�@�i�[��Ζ��̔����ꍇ�͔N�Q��j
�@������N�f�f�̃X�P�W���[������ю��{���@���m�F���Ă����܂��傤�B
���g�D�ύX�A�l���ٓ�
�@�g�D�ύX��l���ٓ����ꍇ�A���łɔ��ߍς݂̂��ƂƎv���܂��B
�@���̂�����Ђł͂R���Q�T�����ٓ����ŁA���܂��܂Ȏv���̌������鎞���ł�����܂����B
�@�l���ٓ��͌o�c���̈ꕔ�Ƃ��āA��Б��̍ٗʂɂ��Ƃ��낪���������ł����A
�ߔN�A��l��l�̏o�Y�E�玙����Ȃǂɂ��ɔz�������Ή����K�v�Ƃ���Ă��܂����B
�@�V�����ߘa�V�N�S���A�P�O���ɉ����̈玙�E���x�Ɩ@�ɂ́A
�_��ȓ��������������邽�߂̑[�u���̋`���t�����F�Z���o�Ă��܂��B
�����^����
�@�S���ɋ��^����������Ђ������ł��B
�@�l���]���Ƃ��̉^�p����ɂ������Ƃ���ł��B
�@�������蓭���Č��ʂ̏o��l�ɕĂ䂭�g�D�ɂ��Ȃ��Ƌt�ɕs�����ɂȂ�ƌ�����Ƃ���ƂȂ�܂��B
�����N�ی����E���ی����̉���
�@�Љ�ی����͎��i�擾����T���ȓ��A�ٗp�ی��͗����P�O���܂łɁA
�NJ��̎����Z���^�[�܂��͔N���������A�NJ��̃n���[���[�N�ɒ�o�̕K�v������܂��B
�@�Ƃ��Ɍ��N�ی��́A��o���x��Ă��܂��ƌ��N�ی��̓K�p���x��Ă��܂��܂��̂ŁA
���߂ɏ�������悤�ɂ��܂��傤�B
���R�U����X�V�̎葱��
�@�R�U��������N���܂��������ɍX�V����K�v����܂��B
�@�x�Ȃ��X�V����悤�ɂ��܂��傤�B
���J���Ҏ����a��
�@�P������R���̊ԂɘJ���ЊQ�Ȃǂɂ��S�l�����̋x�Ƃ����ď]�ƈ�������A
�����̘J����ē��ɒ�o����K�v������܂��B
�@�R�J�����ƂɑΏێ҂�����A��o���܂��B
2025�N3���Q�S���i���j
�ΑӊǗ��V�X�e���@Touch�@On Time�̓����ɂ���
�����J���o�c�������ł́A�ΑӊǗ��V�X�e���@Touch On Time�ɑΉ����Ă��܂��B
Touch On Time�̓����ɂ��w��F�AIC�J�[�h�Ή����ɂ��A
�q�ϓI�����m�ȋΑӃf�[�^�̎擾���\�ł��B
�菑����Excel�ɂ��Ǘ��Ɣ�ׁA�W�v�̂��߂̎��Ԃ�W�v�~�X�̃��X�N��啝�Ɍy���ł��܂��B
�ΑӊǗ����狋�^�v�Z�\�t�g�ւ̘A�g���X���[�Y�ɍs���邽�߁A
�l���J���S���҂̋Ɩ����S��啝�Ɍ��炵�܂��B
�܂��A�N���L���x�ɂ̎c���V�X�e����ŊǗ��ł��܂��B
Touch�@On�@Time�̓����E�^�c�ɂ��ẮA�����J���o�c���������T�|�[�g���܂��B
2025�N�R���Q�R���i���j
�ߘa�V�N�S���E�P�O�������̈玙���x�Ɩ@�̉����ɑΉ�����Ă��܂����H
�@2025�N4���E10���ɂ����āA�玙�E���x�Ɩ@���啝�ɉ�������܂��B
�@�玙�E���x�ƋK���̉�����i�߂Ă����܂����H
�@
�y�{�s���F�ߘa7�N4��1���z
�@�u�q�̊Ō�x�Ɂv→�u�q�̊Ō쓙�x�Ɂv�֖��̕ύX�{���e�g�[
�Ώۊg��F���w�Z3�N�C���܂ł̎q
�擾���R�lj��F�����ǂɂ��w�����A�������E�������Ȃǂ��Ώۂ�
�L���]�ƈ��́u�p���ٗp6���������v���O�K���P�p
�A�玙�ɂ��c�ƖƏ��̑Ώۂ��g��
���s�F3�Ζ����̎q��{�炷��]�ƈ�
������F���w�Z�A�w�O�܂łɊg��
�B�玙���Z���x�̑�֑[�u�Ɂu�e�����[�N�v���V���ɒlj�
3�Ζ����̎q��ΏۂƂ����Z�k�Ζ����x�̑�ւƂ��āA�_��ȓ������̑I����������
�C�玙�E���̂��߂̃e�����[�N�������u�w�͋`���v��
3�Ζ����̈玙�E���Ώێ҂��e�����[�N��I�ׂ�悤�ɂ���[�u���w�͋`����
�D�j���̈�x�擾�����\�`���̑Ώۊg��
���s�F�펞�ٗp1,000�l���̊��
������F�펞�ٗp300�l���ɑΏۊg��
�E��엣�E�h�~�Ɍ������ٗp�������ƌʎ��m�E�ӌ��m�F���u�`���v��
���C�A���k�����ݒu�A���p����̏Љ�A�Г����j�̎��m�Ȃǂ����ꂩ�����{
���ɒ��ʂ����]�ƈ��ւ̌ʎ��m�E�ӌ��m�F���K�{
����ɁA40�ΑO��ł̑��������`����
�y�{�s���F�ߘa7�N10��1���z
�F�_��ȓ������̑I�𐧓x���`�����i�ΏہF3�E���w�Z�A�w�O�̎q��{�炷��]�ƈ��j
��Ƃ͈ȉ���5���ڂ̂���2�ȏ�����{
�E�n�Ǝ����ύX
�E�e�����[�N�i��10���ȏ�j
�E�ۈ�{�݂̐ݒu�^�c��
�E�{��x���x�Ɂi�N10���ȏ�j
�E�Z���ԋΖ����x
�]�ƈ��͊�Ƃ������������x�̒�����1�I�����ė��p��
�����ɂ������ẮA�]�ƈ���\�Ƃ̈ӌ����悪�K�v
�G�D�P�E�o�Y����3�Ζ����̎q��{�炷�鎞���Ɂu�ӌ��̌ʒ���E�z���v���`����
�ӌ�����F�d���ƈ玙�̗����Ɋւ���]�ƈ��̊�]���ʂɊm�F
�z���`���F�m�F�����ӌ����A�Ə����ɔ��f����悤�w�߂�
�R���Q�Q���i�y�j
�p���n���ɂ���
�Q�O�Q�T�N�R���Q�P���i���j
�J�X�^�[�}�[�Y�n���X�����g�ւ̑Ή��ɂ���
���q�l�Ƃ������ƂŔ��_��Ή�������ʂ�����悤�ł��B
��̓I�Ɍ��Ă䂫�܂��傤�B
�J�X�^�}�[�Y�n���X�����g�i�J�X�n���j�Ƃ́A�u�ڋq������Ȃǂ���̎Љ�I�ɕs�K�Ȍ����ɂ���āA�]�ƈ������_�I�E�g�̓I�ȋ�ɂ���s�ׁv���w���܂��B
�ߔN�A�J�����̉��P����^���w���X�ւ̊S�̍��܂肩��A��Ƒ������̖��ɐ^���Ɍ��������K�v���������Ă��܂��B
�� �J�X�^�}�[�Y�n���X�����g�̋�̗�
-
�����Ԃɂ킽��N���[���̓d�b�◈�X�Ή��̋��v
-
�Ј��I�Ȍ�����\���A�l�i�ے�
-
�y�����̋��v�ȂǕs���ȎӍ߂̗v��
-
�Ј��̗e�p�E�N��E���ʂȂǂɑ��鍷�ʓI����
-
SNS�ł̔�排�����N���s��
-
�����ȃT�[�r�X�̗v���i�K��O�̕ԕi�E�ԋ��Ȃǁj
�� �Ȃ����_���ɂ����̂��H
�u���q�l�͐_�l�ł��v�Ƃ����������������A�T�[�r�X�Ƃ�ڋq�Ƃł́A�Ј��������̖�����\���ɑς��邱�Ƃ�“���R”�Ƃ��ꂪ���ł��B
�������A����ɂ���ĎЈ��̌��N����S�����������ꍇ�́A��ƂƂ��Ă��K�ȑΉ������K�v������܂��B
�� �J�X�^�}�[�Y�n���X�����g�ւ̑Ή����@
1. �g�D�Ƃ��Ă̊�{���j�m�ɂ���
-
�u�s���ȗv���E�\���ɂ͉����Ȃ��v���Ƃ��Г��O�ɖ������B
-
�Ј�������Ă���Ɗ�������̐����d�v�ł��B
2. �}�j���A����Ή����[�����쐬����
-
�N���[���Ή��̃t���[�����A�G�X�J���[�V�����̊�m�ɂ���B
-
��l�őΉ��������A��i�⑼�̎Ј����T�|�[�g����̐�������B
3. �Ј��ւ̋���ƌ��C�����{����
-
�J�X�n���̒�`�┻�f��A�Ή����@�����L�B
-
���ۂ̃P�[�X����ɂ������[���v���C���O���C�Ȃǂ��L���B
4. �Ή����̃|�C���g
-
��Â������Ɋ�Â�����������i����I�ɂȂ�Ȃ��j�B
-
�s���ȗv���͋B�R�Ƌ��ۂ���B
-
��b������̋L�^���c���i�^���E�L�^�����Ȃǁj�B
-
�P�ƑΉ�������A��i�ɑ��₩�ɕ���B
5. �@�I��i������ɓ����
-
�����ȏꍇ�͌x�@��ٌ�m�ƘA�g����B
-
���_�ʑ���Ɩ��W�Q�ȂǂɊY������P�[�X�ł͖@�I�Ή����\�ł��B
�� ���q�l�Ƃ̊W��ۂ�������������
�u���q�l���ɂ��邱�Ɓv�Ɓu�s���ȃn���X�����g�������Ȃ����Ɓv�͗����ł��܂��B
�Ј�����邱�Ƃ͌��ʂƂ��ăT�[�r�X�̎����Ƃ̐M���ɂ��Ȃ���܂��B
�K�v�ł���A�J�X�n����̎Г��}�j���A���̐��`�Ȃǂ����p�ӂł��܂��B
�Ǝ��Г��̐��ɍ��킹���Ή������������Ɨǂ��Ǝv���܂����A�������ł��傤���H
�Q�O�Q�T�N�R���Q�O���i�j
�Z�N�n�����������Ȃ����߂�
�����납��Z�N�n���Ɋւ��錤�C�������Ȃ��ȂǁA�Z�N�n�����������Ȃ����߂̊�������������s���K�v������ƌ����܂��B
�Q�O�Q�T�N�R���P�X���i���j
CUBIC�̊��p�ɂ���
�����J���o�c�������ł́A�̗p��l�ޕ]����CUBIC�̊��p�����Ă��������Ă��܂��B
2025�N3��18���i�j
�ЊO�l�����Ƃ��āA�M�Ђ̘J�������͂ɃT�|�[�g���܂��I
�����J���o�c�������́A�M�Ђ�**�u�ЊO�l�����v**�Ƃ��āA�J���Ǘ��̂�����ۑ���������A���S���Ė{�Ƃɐ�O�ł�����Â��������`�����܂��B
✅ �J�����k – �J���g���u���̖��R�h�~����K�ȑΉ��܂ŁA�o�c�ҁE�l���S���҂̔Y�݂Ɋ��Y���܂��B
✅ �J���ی��E�Љ�ی��葱�� – �ʓ|�Ȏ葱���𐳊m���X�s�[�f�B�[�ɑ�s���A�������S���y�����܂��B
✅ ���^�v�Z – ���m�E�v���ȋ��^�v�Z�ŁA�]�ƈ��̖����x�ƐM�������コ���܂��B
✅ �A�ƋK���쐬 – �M�Ђ̎���ɍ��������[�������ŁA�����₷���E������������܂��B
✅ ���������p – ���p�\�ȏ��������Ă��A�o�c�̈���Ɛ������x�����܂��B
�M�Ђ̐l���E�J���̍œK�����A���������S�͂ŃT�|�[�g���܂��I
���C�y�ɂ����k���������B
�Q�O�Q�T�N�R���P�V���i���j
���A�Ⴊ�������̎��Ə��ŁA�������P���Z���c�Ɨ��̌v�Z��b�ɓ���Ă��Ȃ��Ƃ��낪�����悤�ł��A
�Љ�����Ə�ŁA�������P���Z�������v�Z�Ɋ܂߂Ȃ��ȂǁA�@�߈ᔽ���ڗ����Ă���B
2025�N3��16���i���j
���̉��فA������Ƒ҂��Ă��������B
�u���Ј������ĉ��ق������B�v�Ƃ������k���悭����܂��B
�@������Ƒ҂��Ă��������B
�@�\���Ɏw�������܂������H
�@���قɎ���܂łɎ菇�݂܂������H
�@���ʁA�����ɂ͎��̂悤�ȏ���������܂��B
�@�����b�h�J�[�h�͂�قǂ̂��Ƃł��B
�@�܂��̓C�G���[�J�[�h�ł��B
�����̎�ނ͎��̊e���̂Ƃ���Ƃ���B
�@�P�@�@���F�����ɂ���Č��d���ӂ����A���������߂�B
�A梁@�@�ӁF�n�������o�����A���������߂�B
�B���@�@���F�P��̊z�����ϒ����̂P�����̔��z�A���z��������x�����ɂ�����������z���P�O���̂P�ȓ��Ō�������B
�A���A�����̎��Ă���������ꍇ�́A�������ɂ킽���Č������s�Ȃ����Ƃ�����B
�C�o�Β�~�F�P�S����ȓ��̏o�Β�~�𖽂��A���̊��Ԃ̒����͎x����Ȃ��B
�D�~�@�@�i�F���i�������̈�������������B���̏ꍇ�A�J�������̕ύX�����Ƃ�����B
�E�@�|�ސE�F���ӑސE�ɉ�����悤��������B�A���A��������������R�J�����ȓ��ɍ��ӂɒB���Ȃ��ꍇ�͒������قƂ���B
�F�������فF���ٗ\�����Ԃ�݂��邱�ƂȂ������ɉ��ق���B���̏ꍇ�A�����J����ē����̉��ٗ\�����O�F������Ƃ��͗\���蓖���x�����Ȃ��B
�Q�O�Q�T�N�R���P�T���i�y�j
�Œ�c�Ƒ�蓖�̌v�Z
��{���A���Q�T���~�̏]�ƈ��Ɍ��S�T���Ԃ̌Œ�c�Ƒ�蓖��t�^����ꍇ�̌v�Z
�܂��A�����Ϗ���J�����Ԃ��Z�肷��B
�N�ԃJ�����_�[���쐬���Čv�Z����ꍇ�����邪�A
�����ł́A�P�N�R�U�T���A�T�S�O���ԘJ����O��Ɍv�Z����B
�R�U�T��×�S�O����÷�V��÷�P�Q�������P�V�R�D�W����
���������āA�����Ϗ���J�����Ԃ��P�V�R�D�W���ԂƂ��Čv�Z����B
250,000�~÷173.8����×1.25�{×45���ԁ��W�O�C�X�P�P�D�X�U�V�~
�䂦�ɁA��25���~�ɑ���45���Ԃ̌Œ�c�Ƒ�蓖��80,912�~�ƂȂ�B
����͌�45���Ԉȓ��̎c�Ƃł���A80,912�~�̌Œ�c�Ƒ���x�������Ƃ��Ӗ�����B
��45���Ԃ��Ďc�Ƃ�����ꍇ�A���������̎c�Ƒ�͕ʂɎx�������ƂɂȂ�B
�����}�K�@2025�N3��14����
���@�o�c�ҁE�����S���҂̂��߂̃����}�K�@����������������������������
>
> ����������������������������������
> ���l�������J�����������V�����������@�@�@�@�@�@�@�@�@2025�N3��14����
> ��������������������������������������������������������������������
>
> �@���������b�ɂȂ��Ă���܂��B
> �����J���o�c�������̕����p��ł��B
>
> �@����̃����}�K�ł́A36������������ۂ̒��ӓ_�Ƃ��āA���Ⴂ���₷
> ���J���Ґ��Ƌx���J���Ɋւ��鍀�ڂ̈Ӗ��ɂ��ĉ�������j���[�X������
> ��Ă��܂��B���ЁA���e���`�F�b�N���Ă��������B
>
> ��������������������
> �@�{���̃R���e���c�@������������������������������������������������
> ��������������������
> 1.��b�`���Ŋy�����w�Ԑl���J���Ǘ��̊�b�u���F
> �@�@�@�@�d���Ɖ��̗����x�����x�𗘗p����ۂ̉Ƒ��̗v����Ԃ̔��f
> 2.�l���J���j���[�X�F3�Ζ����̎q��{�炷��]�ƈ������p�ł���
> �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�N���z�v�Z�̓���
> 3.�l���J���j���[�X�F36������������ۂ̒��ӓ_
> 4.�������߃��[�t�@�F�ߘa7(2025)�N�x�ٗp�ی������̂��ē�
> ��������������������������������������������������������������������
>
> ������
> ��1.�����d���Ɖ��̗����x�����x�𗘗p����ۂ̉Ƒ��̗v����Ԃ̔��f
> ��������������������������������������������������������������…�d�E
>
> �@�u��b�`���Ŋy�����w�Ԑl���J���Ǘ��̊�b�u���v���X�V���܂����B����
> �͎d���Ɖ��̗����x�����x�𗘗p����ۂ̉Ƒ��̗v����Ԃ̔��f�ɂ�
> �ĂƂ�グ�܂����B���ЁA�������������B
>
> ↓3��13�����J�̉�b�`���Ŋy�����w�Ԑl���J���Ǘ��̊�b�u���F
> �@�@�@�@�d���Ɖ��̗����x�����x�𗘗p����ۂ̉Ƒ��̗v����Ԃ̔��f
> http://m.mkmail.jp/l/i/nk/jzdqjdvoxhhm
>
> ������
> ��2.����3�Ζ����̎q��{�炷��]�ƈ������p�ł���N���z�v�Z�̓���
> ��������������������������������������������������������������…�d�E
>
> �@���q����w�i�ɁA�l�X�Ȍ`�Ŏq�ǂ��E�q��Ăւ̎x�����s���Ă��܂��B
> ����́A�ȑO����݂����Ă�������N���̔N���z���v�Z����Ƃ��̓��ᐧ
> �x�ɂ��ĂƂ�グ�܂��B
>
> ↓3��11�����J�̃j���[�X�̑����͂����炩��I
> http://m.mkmail.jp/l/i/nk/dvnyhmvoxhhm
>
> ������
> ��3.����36������������ۂ̒��ӓ_
> ��������������������������������������������������������������…�d�E
>
> �@�u���ԊO�J���E�x���J���Ɋւ��鋦��v�́A��Ƃ̘J���Ǘ��ɂ����Ă���
> �Ƃ��d�v�ȘJ�g����ł���A���̒����E�͏o���Ȃ���Ȃ����ł̎��ԊO�J���E
> �x���J���A�܂��͋�����e�����E�E�E
>
> ↓3��4�����J�̃j���[�X�̑����͂����炩��I
> http://m.mkmail.jp/l/i/nk/wlbjhkvoxhhm
>
> ������
> ��4.�����������߃��[�t�F�ߘa7(2025)�N�x�ٗp�ی������̂��ē�
> ��������������������������������������������������������������…�d�E
>
> �@����̂������߃��[�t���b�g�́u�ߘa7(2025)�N�x�ٗp�ی������̂��ē��v
> �ł��B2025�N4�����ٗp�ی��������������ƂȂ�܂��B�ڂ����̓��[�t���b
> �g���������������B
>
> ↓�u�ߘa7(2025)�N�x�ٗp�ی������̂��ē��v���܂ސl���J���Ǘ����[�t���b
> �g�W�͂����炩��I
> http://m.mkmail.jp/l/i/nk/t0ykvbvoxhhm
>
> ��…�d�d…��…�d�d…��…�d�d…��…�d�d…��…�d�d…��…�d�d…��…�d�d
> �����W�������L��
> ����������������
>
> �@����A�N��103���~�̕ǂ̌������ɌW��@�Ă��O�c�@�{��c�ʼn�����A��
> �X����錩�ʂ��ƂȂ�܂����B�]�ƈ��̊S�������A���^�v�Z��N�������ɂ�
> �e������̂ŁA��������Ə����������Ă����K�v������܂��ˁB
>
> ��������������������������������������������������������������������
> �� �s ���F�����J���o�c������
> �@�@�@�@�@�@��631-0805�@�ޗnj��ޗǎs�E��4����4-19
> �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
> �@�@�@�@�@�@�@�@TEL 0742-71-8936
> �� �s �l�F�����p��@info@f-roumu.jp
> �z�[���y�[�W �Fhttp://www.fukuoka-roumu.com/
> ��������������������������������������������������������������������
> �����ЁA���ӌ��E�����z��info@f-roumu.jp�܂ł����肭�������B
> �������N��́A���ׂē��������̃z�[���y�[�W�ƂȂ��Ă���܂��B
> ��������������������������������������������������������������������
>
2025�N3��14��(���j
�玙�E���x�ƋK���̉�����i�߂Ă��܂��B
�@�ߘa7�N4���y��10���Ɉ玙�E���x�Ɩ@�̉������s���܂��B
�@����ɐ旧���A�����J���o�c�������ł́A�玙�E���x�ƋK���̉�����i�߂Ă��܂��B
�@���S���Č����A�D�P�A�o�Y�A�玙���ł���Љ�ɂ��邱�Ƃ��ɂ߂ďd�v�Ȃ��Ƃ͘_��҂��܂���B
�@�܂��A��엣�E���Ȃ����Љ�ɂ��邱�Ƃ��ɂ߂đ�ł��B
�@�玙�E���x�Ɩ@�͏��q����Љ�̖����y�����邽�߂̏d�v�Ȗ@���ł��B
�@�������������ĔD�P�A�o�Y���Ă��������Ƃ��p���ł���̂́A�玙�E���x�Ɩ@�̗��t��������A
�玙�x�Ƃ�O�ɂƂ�鎞��ɂȂ������Ƃ��傫���ƌ����܂��B
�@�܂��A�j���̈玙�x�Ƃ�����Ɛi��ł��܂����B
�@�j���̈玙�x�Ƃ̎擾�����\����`���́A
����̖@�����ŏ]�ƈ���1000�l���̊�Ƃ���300�l���̊�ƂɊg�傳��܂��B
�@��엣�E�h�~�̂��߂̌ٗp���������`��������܂����B
�@���ׂĂ̊�Ƃ��玙�E���x�Ɩ@�̓��e�𗝉�����ƂƂ��ɁA
�玙�E���x�Ƃ̉������K�v�Ƃ����Ƃ���ł��B
�Q�O�Q�T�N�R���P�R���i�j
�@������Ƃ̑ސE�����x�ɂ���
�@������ƑސE�����ϐ��x�Ɨ{�V�ی��̂Q���̂P�����̓���
�悭�g����̂͒�����Ƌ��ϐ��x�Ɨ{�V�ی��̂Q���̂P�����ł��B
���ꂼ��̓����ɂ��ďq�ׂ܂��B
��������ƑސE�����ϐ��x�̓���
�i�����b�g�j
�@�S�z���o��ŗ�����B
�@�����A�|�����������ł���A�ȕւł���B
�@�]�ƈ��ɂƂ��Ă��킩��₷���B
�i�f�����b�g�j
�@�ςݗ��Ă��|�����͂��Ƃ��������ق̂悤�ȏꍇ�ł��A�]�ƈ��ɓ���B
�@�\���ɂ��x�����Ȃ����Ƃ����蓾�邪�A���̏ꍇ�ł������͍��ɂ͂���B
�@�����͓���Ȃ��B�i���������ŏ]�ƈ����̋������͓̂����ꍇ������j
���{�V�ی��̂Q���̂P����
�i�����b�g�j
�@��\������������B
�@���S�ی����͏]�ƈ��̈⑰�Ɏx������邪�A
�@����������Ԗߋ��͂��������Ƃɓ���̂ŁA�ٗʐ�������B
�@��N�N��ɍ��킹�ċ��z��I�ׂ�B
�@�|�����̂Q���̂P�������ɂȂ�B
�@�Q���̂P�͑ސE�ی��ϗ����Ƃ������`�Ŏ��Y�v��ɂȂ�B
�i�f�����b�g�j
�@���i�A�݂�����Ȃ��B
�@�ȏ�A�������̍ޗ��ɂ��Ă���������Ƒ����܂��B
�@�Ȃ��A�����J���o�c�������͒�N�̂U�O�ɍ��킹�A
�{�V�ی��̂Q���̂P�����ɉ������Ă��܂��B
�@�l���Ǝ�ł��̂ŁA�����p�ꂪ�_��҂ɂȂ�܂��B
�@�{�V�ی��̏ꍇ�A�����ς�̍쐬���\�ł��B�@
�Q�O�Q�T�N�R���P�Q���i���j�ߘa�V�N�x�������P���Z�͂S���P�T�����ߐ�ł��B
�V�����⏕�����o�܂��B
�ߘa�V�N�x�������P���Z�̎���������Ă��܂����B
��N�U�����珈�����P���Z�A���菈�����P���Z�A�x�[�X�A�b�v�����Z����{������A
�V�������x�Ɉڍs���܂����B
���N�́A�������P���Z�Ƃ͕ʂɁA�l�ފm�ہE�E������P�����ƌv�揑�̒�o�ɂ��A
�⏕�����x������邱�ƂɂȂ�܂����B
���̕⏕���͈ꎞ���Ŏx�����܂��B
�l����ɏ[�����邱�Ƃ��\�ł����A�E������P���Ƃ̂��߂Ɏg�����Ƃ��\�ł��B
�v��\���ɓ���Y�܂����Ə��������ł����A�����J���o�c�������ł́A
�������P���Z�v�揑��⏕���̎x�����邽�߂̐\���x�����s���Ă��܂��B
2025�N�R���P�P���i�j
�玙�E���x�Ɩ@�̉����A�ߘa�V�N�P�O�������̒��̍���
�_��ȓ��������������邽�߂̑[�u�ɂ���
��Ђ́A�ߔ����J���ґ�\�̈ӌ�����̋@���݂��A
�@����⓹�̒�����A�Q�ȏ�̑[�u��I������K�v������܂��B
�@�[�P�@�n�Ǝ������̕ύX�i�����o�ΐ��x�j
�@�[�Q�@�t���b�N�X�^�C����
�A�e�����[�N��
�B�{�痼���x�����x�E�E�E�q�̗{��̂��߁A�N���L���x�ɂƂ͕ʂɎ擾�ł��鐧�x�B
�@�@�P�N�ԂɂP�O�������x�Ƃ��ċK�肷��B
�C�Z���ԋΖ����x
�D�[�P�ۈ�{�݂̐ݒu�^�c
�D�[�Q�x�r�[�V�b�^�[�̎�z����є�p�⏕
�Q�O�Q�T�N�R���P�O���i���j
�玙�E���x�Ɩ@�̉����ɂ���
�Q�O�Q�T�N�S���P���̉������e�͎��̂Ƃ���ł��B
���玙�ɂ�����������e
�@�q�̊Ō�x���̌������@���A�ƋK�����������܂�
�E�擾�ΏۂƂȂ�q�͈̔͂����w�Z3�N���C���܂łɊg��
�E�擾���R�Ƃ����u�����ǂɂ��w�����v���u�����E���w���A�������v�Ȃǂ�lj�
�E�p���ٗp����6���������̘J���҂ɑ��鏜�O�K���P�p
�E���̂��u�q�̊Ō쓙�x���v�ɕύX
�A����O�J���̐����i�c�ƖƏ��j�̑Ώۊg���@���A�ƋK�����������܂�
�E3�Ζ����̎q��{�炷��J���҂̂ݑΏ� → ���w�Z�A�w�O�̎q��{�炷��J���҂Ɋg��
�B�Z���ԋΖ����x(3�Ζ���)�̑�֑[�u�Ƃ����e�����[�N�lj��@���Ή��s�v
�E�Z���ԋΖ�������ȋƖ��ɏ]������J���Ҍ����̑�֑[�u�Ƃ��ăe�����[�N���\��
���A�ƋK���ɂĊ��ɒZ���ԋΖ����x�̋K��������ꍇ�A��֑[�u�͕K�v�͂���܂���B
�C�玙�̂��߂̃e�����[�N�����@���Ή��s�v
�E3�Ζ����̎q��{�炷��J���҂ɑ��A�e�����[�N��I���ł���悤���Ǝ�ɓw�͋`�����ۂ� ���w�͋`���ł��̂ŁA�Ή��ł��Ȃ��Ă����͂Ȃ��B
�D�玙�x�Ǝ擾�̌��\�`���̊g��@ �E�`���Ώۊ�Ƃ��]�ƈ���1,000�l������300�l���Ɋg��
���ɂ�����������e
�E���x�ɂ̗v���ɘa�@���A�ƋK�����������܂�
�E�p���ٗp����6���������̘J���҂ɑ��鏜�O�K��̔p�~ �F��엣�E�h�~�̂��߂̌ٗp�������̋`�����@���A�ƋK�����������܂�
�E���Ǝ�͈ȉ��̂����ꂩ�̑[�u���u����K�v���� �@
�A.���x�ƁE���x�����x�Ɋւ��錤�C�̎��{ �@
�C.���x�ƁE���x�����x�Ɋւ��鑊�k�̐��̐����i���k�����̐ݒu�j
�E.���x�Ǝ擾�E���x�����x�̗��p����̎��W�E�� �@
�G.���x�ƁE���x�����x�̗��p���i�Ɋւ�����j�̎��m
�G���Ɋւ���ʎ��m�E�ӌ��m�F�̋`�����@�������Ή��K�v
�E���ɒ��ʂ����J���҂ɑ��āA�ʂ̎��m�Ɨ��p�ӌ��̊m�F���`����
�E40�Γ��B���̏��`����lj� �H���̂��߂̃e�����[�N�����@���Ή��s�v
�E�v����Ԃ̑ΏۉƑ�����삷��J���҂��A�e�����[�N��I���ł���悤���Ǝ�ɓw�͋`�����ۂ�
�@���w�͋`���ł��̂ŁA�Ή��ł��Ȃ��Ă����Ȃ��B
���ɁA�P�O���̉������e�͈ȉ��̂Ƃ���B
���玙���̏_��ȓ��������������邽�߂̑[�u�̋`�����@���Ή��K�v(�q�A�����O�V�[�g�ł��ӌ�������������������)
3���珬�w�Z�A�w�O�̎q��{�炷��J���҂ɑ��A�ȉ��̑I�����̒�����2�ȏ�̑[�u���u����`����
�@�n�ƁE�I�Ǝ����̕ύX�i�t���b�N�X�^�C�����A�����o�Ȃǁj
�A�e�����[�N�̓����i��10���ȏ�̗��p���\�Ȑ��x�j
�B�ۈ�{�݂̐ݒu�E�^�c�A�܂��̓x�r�[�V�b�^�[�̎�z�x��
�C�{�痼���x���x�ɂ̕t�^�i�N10���ȏ�j
�D�Z���ԋΖ����x�i����̏���J�����Ԃ�����6���ԂƂ���j �J���҂͎��Ǝ傪�u�����[�u�̒�����1��I�����ė��p�\ �[�u��I������ہA�ߔ����J���g�����̈ӌ����悪�K�v
���玙�Ǝd���̗����Ɋւ���ʂ̈ӌ�����E�z���@�������Ή�
�J���҂̔D�P�E�o�Y�\�o������юq��3�ɂȂ�O�̓K�Ȏ����Ɍʈӌ��̒���`���� ���悷����e
�E�Ζ����ԑсi�n�Ƃ���яI�Ƃ̎����j
�E�Ζ��n�i�A�Ƃ̏ꏊ�j
�E�����x�����x���̗��p����
�E�d���ƈ玙�̗����Ɏ�����A�Ə����i�Ɩ��ʁA�J�������̌��������j ���Ǝ�͒��悵���J���҂̈ӌ����l�����A�\�Ȕ͈͂Ŕz�����邱�Ƃ����߂���B
�Q�O�Q�T�N�R���X���i���j
�p���[�n���X�����g�i�p���n���j�ɂ���
���Q�O�Q�T�N�R���W���i�y�j
�@�ΑӊǗ��A�葱���Ɩ��A���^�v�Z���N���E�h��ʼn���
�@�����J���o�c�������ł́A�ΑӊǗ���Touch on Time���g���ăN���E�h��ōs�����Ƃ������B
�@�N���L���x�ɂ̎c�Ǘ���Touch�@on�@Time�ōs����B
�@�����ɂ������Ă��A�w�����s���Ă���B
�@���^�v�Z���}�l�[�t�H���[�h���g������B
���^�v�Z���ʂ͐E��������N���E�h��Ō����̂ŁA�y�[�p�[���X�����������Ă��邱�Ƃ������B
�@Touch�@on�@Time�Ƃ��A�g���Ă���B
�@�J���ی���Љ�ی��̎葱�����I�t�B�X�X�e�[�V�����ōs���B
�@�ʓ|�Ȏ葱���������J���o�c���������d�q�\��������̂Ő��m�E�v���ɂł���B
�@
�@Touch on Time�ɂ��ΑӊǗ��A�}�l�[�t�H���[�h�ɂ�鋋�^�v�Z�A
�@�I�t�B�X�X�e�[�V�����ɂ��J���ی���Љ�ی��̎葱���͂��ꂼ��q�����Ă���A
�@�N���E�h��ŏ������ł���B
�@
���Q�O�Q�T�N�R���V���i���j
�@�U�T�Β��ٗp���i�������@���N��Җ����ٗp�]���R�[�X
�@�T�O�Α�̗L���_��Ј����������A���p�ł��鏕�����ł��B
�@�T�O�Έȏォ��N�N����̗L���_��Ј����ٗp�Ј��ɓ]�������邱�Ƃɂ���Ă��炦�鐧�x�ł��B
�@�ߘa�T�N�x���Ɍv��\��������A�P�l�ɂ��S�W���~�x������܂������A
�ߘa�U�N�x�ȍ~�́A�P�l�R�O���~�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�����͊e�s���{���̓Ɨ��s���@�l�@����E��Q�E���E�Ҍٗp�x���@�\�ɂȂ��Ă��܂��B
�@��x�A���k����Ă͂������ł��傤���H
�@���邢�́A���������悭�����Ă���Љ�ی��J���m�ɐu���Ă݂Ă͂ǂ��ł��傤���H
���Q�O�Q�T�N�R���U���i�j
�@���A�Ⴊ���������Ƃɂ����鏈�����P���Z�̎��g�݂����悤�I�I
�@��N�A�U�����珈�����P���Z����{������A���Ȃ�V���v���ɂȂ����B
�@���낻��A�ߘa�V�N�x�������P���Z�̏��������悤�B
�@�S���A�T������̏������P���Z�v�揑�̐\���͗ߘa�V�N�S���P�T�������ߐ�ƂȂ��Ă���B
�@���N�͍�N�Q������T���̓����t���ɑ����āA
�J�����̉��P��l����ɏ[�����邽�߂̕⏕�����ꎞ���Ŏ擾�ł��邱�ƂƂȂ����B
�@�悭�킩��Ȃ����Ə�����͐��̎Љ�ی��J���m�ɂ��肢����̂������B
�@�����J���o�c�����������N�A�������P�v�揑�̍쐬�A�����āA�������P���ѕ̎x���������Ă��������Ă��܂��B
���Q�O�Q�T�N�R���T���i���j
�@��엣�E���Ȃ������I�I
�@�玙�x�Ƃɂ��ẮA���Ȃ�蒅���Ă����B
�@�j���̈玙�x�Ƃ��@���̌㉟���������āA�F�m�������݂���B
�@�Ƃ��낪�A���x�Ƃ̊��p�ƂȂ�Ƃ��܂����̊�������B
�@���x�Ƃ͂X�R���擾�ł��A���R��ɕ����Ď�邱�Ƃ��ł���B
�@���̐��x��m�芈�p�����������ŁA��엣�E��Ƃꂽ�l���݂Ă����B
�@�܂��A��Ђ͐E�������x�Ƃ��擾�������ƕ��A�������ɁA
�����������鐧�x������B
�@��Ђ��E����������x�Ɛ��x���g���āA��엣�E�̕s���̉������͂��肽�����̂ł���B
���Q�O�Q�T�N�R���S���i�j
�@�玙���x�Ɩ@�̗ߘa�V�N�S���A�P�O�������ɂ���
�@�玙�E���x�Ƃ��ߘa�V�N�S���A�P�O���ɉ����ɂȂ�܂��B
�@����A���Ɠ��N�z��M�q����Ƙb���܂����B
�@M�q����͑�萶�ۉ�Ђ̎���������ł����B
�@�D�P���ďo�Y����Ζ�����A��N������d��������Ă��܂��B
�@�����A�{���ɏo�Y����Ζ�����̂��Ƃ������ƂŁA����������ɂ܂ŗ���ꂽ�����ł��B
�@�����ɂ��ގЁA�o�Y�ɂ��ގЂ�������O�ł���������B
�@����Ȃɐ̂̂��Ƃł͂���܂���B
�@���́A�o�Y����A�Ƃ���̂�������O�̎���ɂȂ�܂����B
�@���S���āA�o�Y���ł��A���A�ł����Ђɂ��Ă䂫�܂��傤�B
�@�Ɠ����ɁA�j�����玙�x�Ƃ��擾����̂��蒅������܂��B
�@�j������������������蒅���܂����B
�@�V��������ɑΉ��ł���悤�A�玙�E���x�ƋK�����������萮�����Ă����܂��傤�B
���Q�O�Q�T�N�R���R���i���j
�@HP�̃��j���[�A���ɂ���
�@HP�����j���[�A�����܂����B
�@���ƂɈς˂邱�Ƃ��l���܂������A�����̎���ō쐬���܂����B
�@�l���J���A�����W�̎ЊO�l�����Ƃ��Đ��i���Ă䂫�܂��B
�@���������A��낵�����肢���܂��B